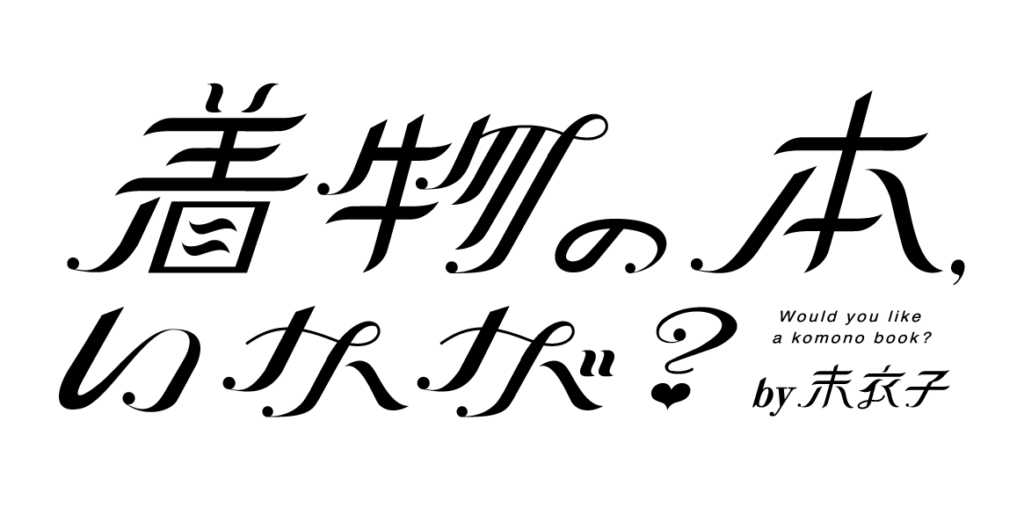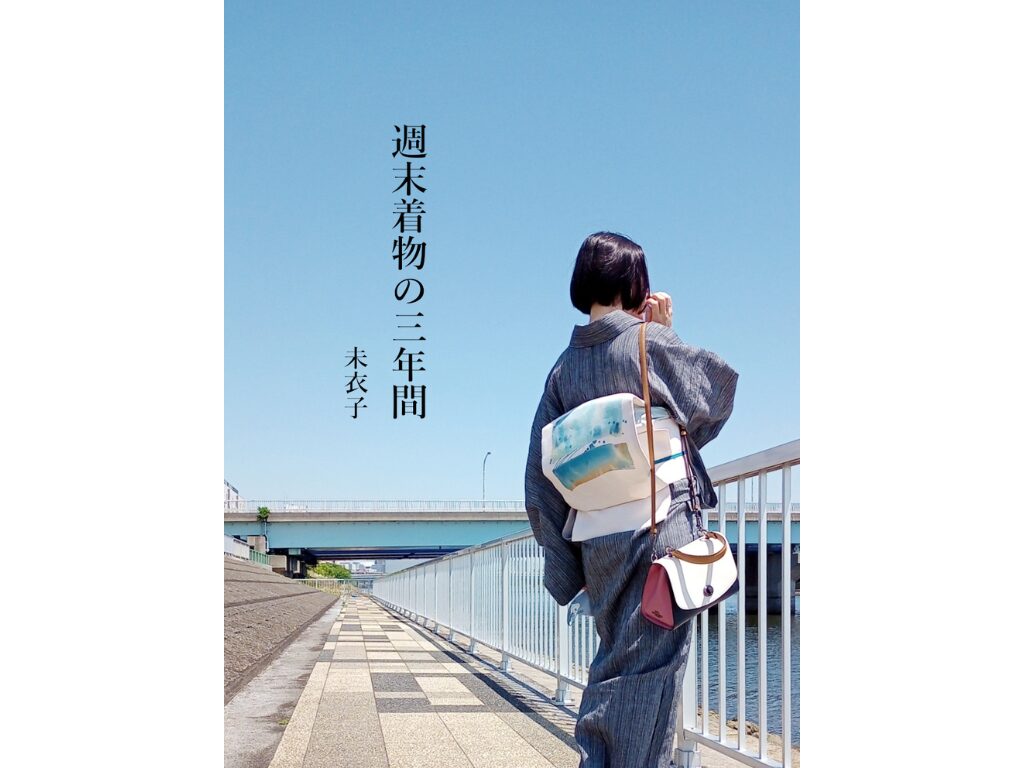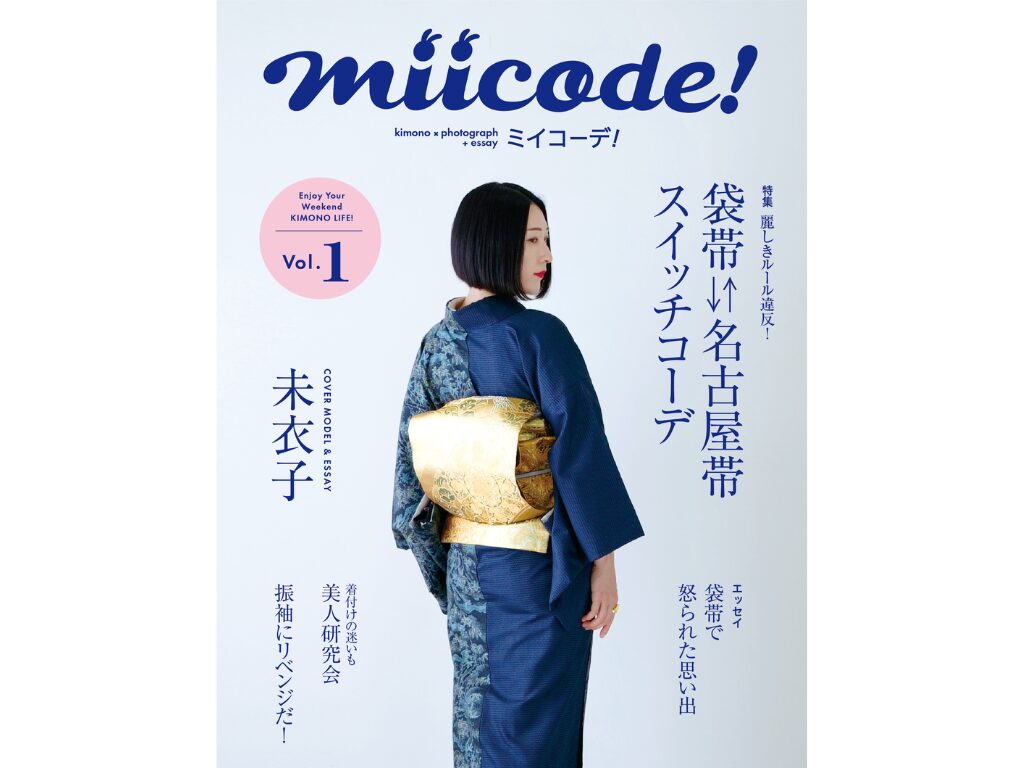前回選んだ現代物の秩父銘仙が、ついに仕立てあがりました!
反物の時点でも十分な魅力を感じましたが、こうして着物の形になると、雰囲気が大きく変わりますよね。お仕立てって不思議! やはり、人が着るもの(=きもの)になることで、品物としての意味合いが違ってくるのでしょうか。そんな反物の変身を見られるのも、お仕立ての楽しみの一つかもしれません。
仕立て上がった現代物の秩父銘仙

こんな感じに仕立て上がりました。「埼玉では今、こんなに素敵な着物が作られています!」とみんなに自慢したくなりますね!

大きな花が立体的に浮かび上がる、迫力ある柄行の銘仙。肩や両袖などの目立つところに「夢の花」が集まるように仕立てていただきました。


コーディネートでは、銘仙の迫力に負けない帯を選ぶのがコツだそうです。手持ちの帯はもちろん、これから先に買う帯まで、銘仙とコーデするのが楽しみになってきました!

八掛には納戸色を選びました。わたしの手持ちアイテムには青系の帯締め・帯揚げが多いので、八掛とばっちり色を揃えてコーデできそうです。あるいは、帯周りをモノトーンでコーディネートしたときも、いい差し色になってくれそう!

お気に入りの黒字に唐草模様の長襦袢との相性もご覧の通りです。それにしても、着物って細部までもれなく綺麗でうっとり……。
銘仙の生地には表裏がない!

銘仙は「ほぐし捺染」と呼ばれる先染めの技法で色がつけられています。そのため、生地に表裏がないのも特徴の一つなのです!
このように着物の余りぎれをめくって見比べると、どちらの面も同じように染まっていて、素人目にはどちらが表だか裏だかわかりません。きっと単衣で仕立てても綺麗でしょうね。
秩父銘仙の余りぎれを額装してみた

お気に入りの反物の余りぎれは、額装して楽しむ方法もあるそうです。
こうして買ってきた額に入れると、和室向けのおしゃれなインテリアのできあがり! 和モダンな雰囲気にしたかったので、洋風寄りのデザインの額を選んでみました。額の大きさやデザイン、飾り方によっても雰囲気が大きく変わりそうですね。
自宅の桐箪笥の上に飾ったので、これからは着付けするたびに秩父銘仙を眺められるようになりました♡
前編・後編もご覧ください♡
おまけ
着物を題材にした小説を書きました。ほんの少しですが、秩父銘仙も登場します。作品の紹介ページもご覧になっていただけたらうれしいです!
SNSで着物コーデを投稿しています。ぜひフォローしてください!
販売中の本
このブログには、広告・PR等を掲載していません。書籍の売上によって運営を行っています。
エッセー『週末着物の五年間』
週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。
エッセー『週末着物の三年間』
埼玉県の最北端で元気に遊ぶ着道楽のエッセーです。週末着物生活3年目の頃に書きました。着物を着る方には、きっとクスッと笑ったり共感したりと、身近に感じて楽しんでいただけるのではないでしょうか。読めばきっと着物生活を根気よく続けるヒントが見つかるはず。
着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』
『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。
Online Shop