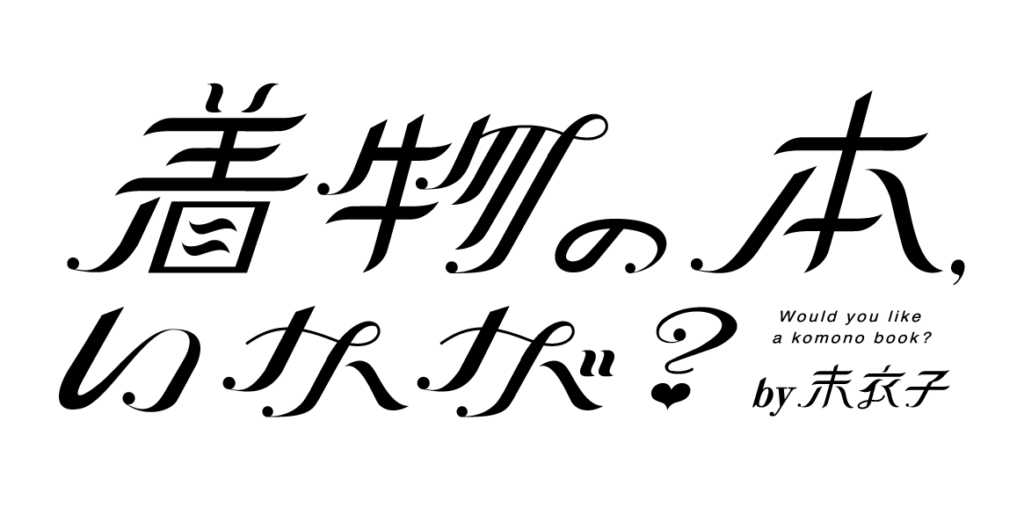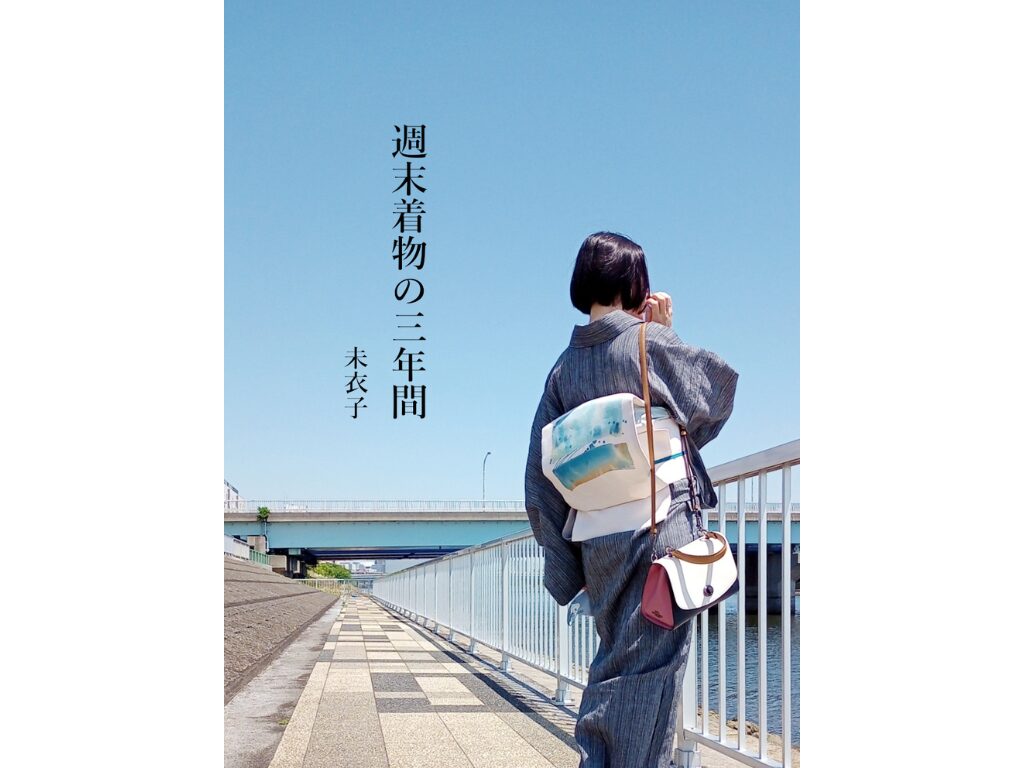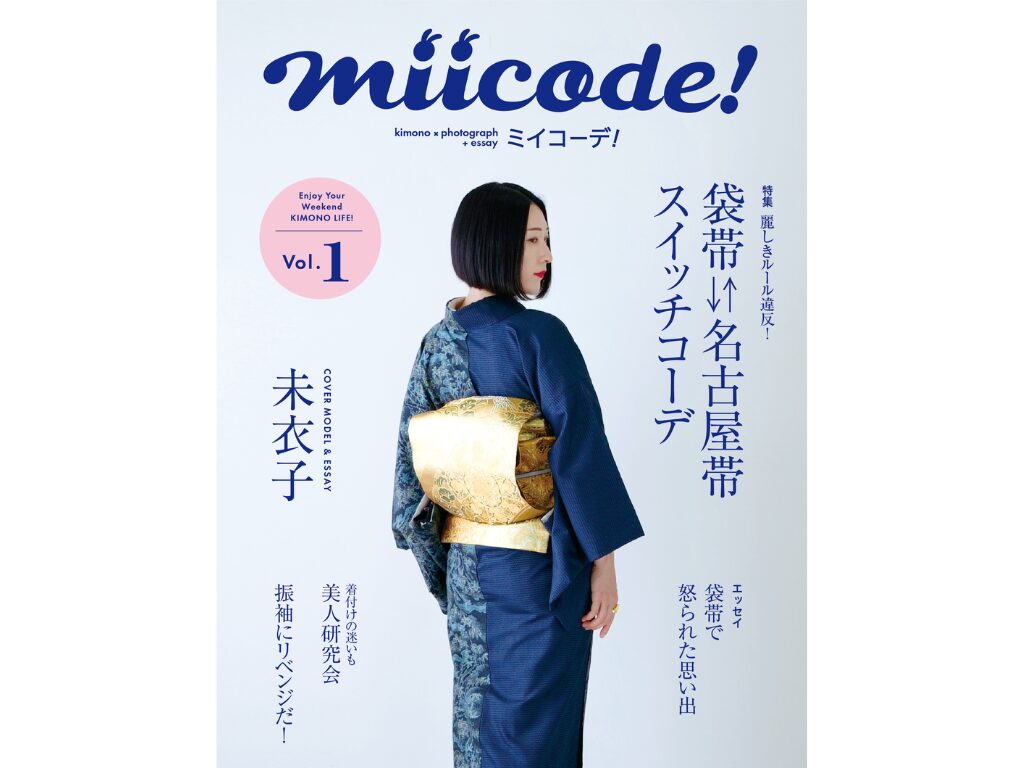前回仕立て上がった現代物の秩父銘仙を着て、秩父へ着物の里帰りをしてきました!
この日は、織元の新啓織物さんとお会いするイベントに参加しました。主催は「きものこすぎ」さんで、ドレスコードはもちろん新啓織物の秩父銘仙です!
熊谷から秩父へ向かう一行

数年ぶりに秩父へ。車で1時間と少し走るだけなのに、しっかりと小旅行の気分に浸れるのが我らが秩父。すでに袷の季節ではあるものの、熊谷は少し汗ばむくらいの気温でした。秩父へ行けば多少涼しくなるかと期待していましたが、やはり暑い! 現地で待っていた新啓織物さんいわく「熊谷が暑い日には、秩父も暑いですよ」とのことです。(笑)
仕立てあがった秩父銘仙で初めて出かけるのも楽しみでしたが、ほかの方の秩父銘仙コーデを見るのも楽しみで……。普段から人様のお召し物が気になって、ついジロジロ見てしまうわたし。着物ファンのパーティーでは、みなさんさすがに街中で見られ慣れていらっしゃるのだし、ジロジロ見ても快く許してくれますよね?
秩父銘仙率着用率100%のパーティー

パーティー会場では、織元さんも、着物ファンも、着物屋さんも、全員がもれなく秩父銘仙を着ています。驚異の秩父銘仙着用率100%!
自己紹介では、一人ひとりが自分の選んだ秩父銘仙への想いを熱く語りました。それを聞いている織元さんは、はにかんだような表情でうんうんと頷きます。ああ、なんて素敵な時間なのかしら。
着物に限らず、どんなお気に入りの服にだって世界のどこかに必ずそれを作った人がいます。でも、その人に自分から直接的に感謝を伝えるチャンスはなかなかありません。こうして自分たちが着物を楽しんでいる様子を知っていただけて幸せでした。
秩父銘仙の織元さんに質問してみた

せっかく織物さんとお話しできる貴重な機会なので、気になっていたことを質問してみました!
| Q.現代物の銘仙には、アンティークの銘仙のような模様のずれが少ないように見えますが、なにか違いはあるのでしょうか? A.「ずれのないほうが技術が高い」という考え方のもとで、しだいに織る機械や技術が改良されてきました。 |
ただし、織物さんの話しぶりからは、単に「ずれがないほうが好ましい」というわけではないという印象を受けました。
きっと銘仙ファンの方には伝わるかと存じますが、ほぐし捺染ならではのずれも着物の表情の一つです。現代物のなかにも、ずれの味わいを生かした品物はありますし、アンティーク銘仙ならではのずれ感に魅力があるのは言うまでもないでしょう。


現代に続く秩父銘仙にできる表現の豊かさとして、織元さんが想像よりも遥かに多くのエッセンスを大切にされていることがわかりました。
秩父銘仙は織り方にも秘密が!

ちなみに、わたしの選んだ秩父銘仙は紫色がチャームポイントとのこと。緯糸に黒を使うことで立体的な色味に仕上げているのだそうです。この深みのある紫の色味が、まさか織り方によって生み出されていたとは!
また、ほかの着物ファンの方が着ていた秩父銘仙には、経糸と緯糸の色使いの工夫により玉虫のように光って見える「玉虫織」のものもありました。まるで、変色する宝石アレキサンドライトを思わせるミステリアスな一着ですね。

最後に、秩父銘仙を着た着物ファンの集合写真を。同じ秩父銘仙でも、こんなに色んな着こなしがありますよ!
前編・中編もご覧ください♡
おまけ
着物を題材にした小説を書きました。ほんの少しですが、秩父銘仙も登場します。作品の紹介ページもご覧になっていただけたらうれしいです!
SNSで着物コーデを投稿しています。ぜひフォローしてください!
販売中の本
エッセー『週末着物の五年間』
週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。
エッセー『週末着物の三年間』
埼玉県の最北端で元気に遊ぶ着道楽のエッセーです。週末着物生活3年目の頃に書きました。着物を着る方には、きっとクスッと笑ったり共感したりと、身近に感じて楽しんでいただけるのではないでしょうか。読めばきっと着物生活を根気よく続けるヒントが見つかるはず。
着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』
『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。
Online Shop